Service
業務案内
相続登記・遺言作成
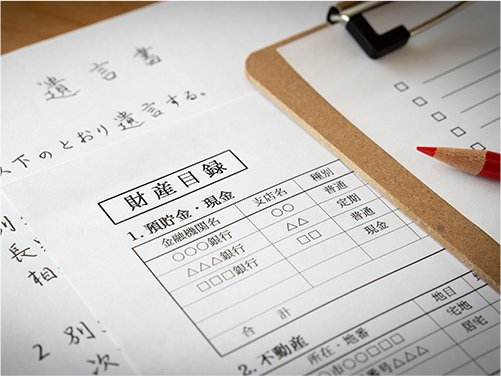
「相続」とは
人が死亡すると、「相続」が開始します。 相続とは、死亡した人(「被相続人」といいます。)の一切の権利義務(「相続財産」)を「相続人」が受け継ぐことです。
「相続財産」とは
相続の対象となる財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。 例えば現金、預金、不動産(土地・建物)といったものはもちろん、借金のような負の財産も含まれます。これを「相続財産」といいます。
「相続人」について
どのような場合に、誰が相続人になるかは法律(民法)で定められています。 また、相続人のうち、誰がどのような割合で財産を相続するかという割合を相続分といい、これも法律で決まっています(「法定相続分」といいます。)。 具体的には、次のとおりです。
| 順位 | 血族相続人 | 配偶者 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子(相続分2分の1) | 配偶者(相続分2分の1) |
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(相続分3分の1) | 配偶者(相続分3分の2) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹(相続分4分の1) | 配偶者(相続分4分の3) |
被相続人の親族のうち、一定の範囲にある人が相続人になります。
配偶者(夫や妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。「血族相続人」については先順位の人がいない場合に次の順位の人が相続人になります。
つまり、子どもがいる場合は子どもが、いない場合は直系尊属(親など)が、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は、「遺言」によって変更することができます(遺言で指定された相続分を「指定相続分」といいます。)。
相続の手続き(遺産分割協議)
被相続人が「遺言」を残している場合は、遺言に従って相続の手続きを進めていきます。
遺言がない場合で相続人が複数の場合は、話し合いをして誰がどの財産を相続するかを決めることになります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議をした記録(書面)のことを「遺産分割協議書」といいます。遺言があっても遺産分割協議が必要な場合もあります。
遺産分割協議は法定相続分に従う必要はありません。法定相続分が3分の1の人が2分の1を相続することも、逆に全く相続しないこともできます。
これに対して相続人という地位は、相続放棄等の手続きによらなければ失うことはありません。
「財産はいらない」旨を決めていても、遺産分割協議には参加しなければなりませんし、特定の相続人を除外して遺産分割協議をしてもその協議は無効です。
土地建物の名義変更(相続登記)
相続した財産がお金などであれば現金で持ち帰ったり自分の口座に入れることができます。それに対して土地や建物など不動産を相続した場合はどうすればよいでしょうか。
法律的には、遺産分割協議で不動産を相続したことが分かれば、その不動産はその相続人のものであることは証明されます。
しかしその不動産を売却したり、担保に入れたりするためには、法務局などに備付けの「登記簿」上で、その不動産がその人の所有であることを明らかにしておく必要があります。
相続を原因として登記簿の不動産の名義を変更することを「相続登記」といいます。
2024年(令和6年)4月1日から、法律改正により、相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記をしない場合には10万円以内の過料が科せられる場合があります。
ただし、相続登記をしなくても過料を免れる方法があります。くわしくはお問合せください。
相続登記の手続き
相続登記を行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄抄本、遺産分割協議書などが必要になります。
具体的な相続登記の手続きは、被相続人名義の不動産の調査、必要書類の収集、申請書の作成など複雑な作業を多く要する場合があります。
当事務所では不動産の調査から登記申請まで、一括して受任しております。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に対して、相続人の地位を放棄することを申述する手続きです。
相続財産には、現金、預金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
借金ばかりが残っているので相続人の地位そのものを放棄したい、という場合にはこの手続きによることができます。
相続放棄には、相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続きをしなければならないという制限がありますのでご注意ください。
また、相続放棄した場合には初めから相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議に参加することもできなくなります。
遺言作成について
被相続人が遺言を残していなかったため、相続財産を巡って相続人等の遺族間で紛争が生じるケースは少なくありません。
紛争を予防するには、遺言を残しておくことが最も効果的です。
ただし、遺言はあくまでも遺言者本人の意思によらなければなりません。本人の意思によらない遺言は無効です。
当事務所では遺言に関するご相談から遺言文案の作成まで一貫してサポートいたします。
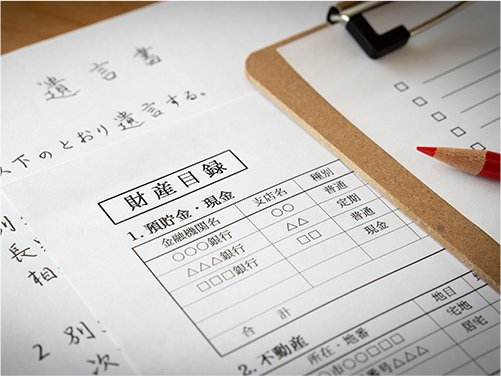

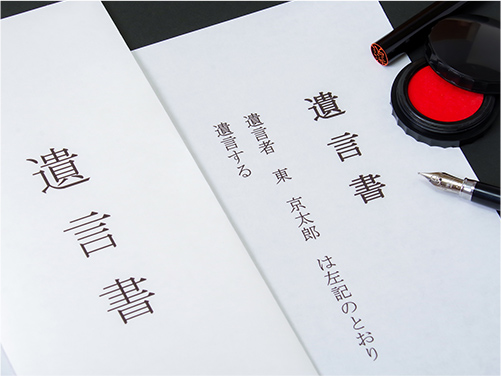
不動産の登記(売買、贈与など)
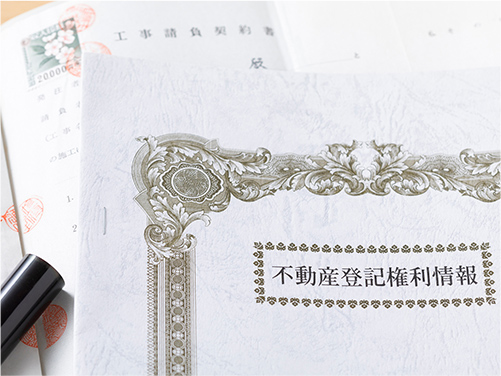


相続以外の不動産の登記
相続以外でも、売買や贈与、住宅の新築・住宅ローンの借入・返済などで登記が必要になる場合があります。
売買や贈与での不動産の名義変更
「知り合いから土地を購入した(売買)」、「家を息子に生前贈与した」といった場合、法律的には不動産の「所有権が移転した」ということになります。
「所有権が移転した」場合、法律的に必ず登記簿上の名義を変更しなければならないわけではありませんが、当事者以外の第三者に所有権が移転したことを主張するためには、登記簿上の名義を新所有者に変更しなければいけません。
売買では、代金の支払いと引きかえに登記名義を変更するという契約を結ぶことが通例です。
登記名義の変更には専門的な知識が必要です。
当事務所では契約の段階から登記名義変更の完了までお客様をサポートいたします。
また、売買や贈与には税金がつきものです。
当事務所では、信頼できる税理士と提携しておりますので、ワンストップで税金問題のご相談にも対応いたします。
住宅(建物)を新築したら
マイホームを新築したりして住宅ローンを組む場合、金融機関との契約で、新築した家や敷地を抵当に入れた旨を登記しなければならないことがほとんどです(「抵当権設定登記」といいます。)
当事務所では、税理士との連携により、登記手続だけでなく、住宅資金の贈与や住宅ローン控除等の税負担についてのご相談についても対応いたします。
住宅ローンを完済したら
住宅ローンを完済すると、「抵当権設定登記」を「抹消」することができるようになります。
この抹消の手続きをしておかないと、登記簿上、いつまでも抵当権が残ってしまいます。
住宅ローンは残っていなくても、登記簿を見た人には、まだローンを払い終わっていないように見えてしまいますので、抹消の手続きをしておくことをお勧めします。
抵当権抹消の手続きはそのままでは金融機関にしてもらえるわけではありません。
当事務所までご相談ください。
債務整理(借金問題)
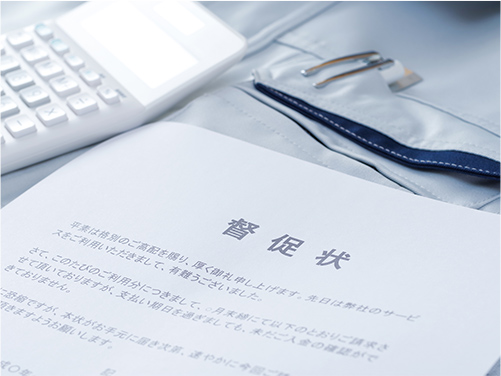
借金問題でお困りの方
借金問題は、必ず解決できます。解決に至る道筋は次のようになります。
相談
まずは、ご相談ください。
相談時には、借金の相手方・金額、借金をした事情・時期、現在の家計 ・財産の状況等の事情をうかがいます。
委任契約
相談の結果、費用等について合意すれば、債務整理委任契約が成立します。
債権(債務)調査
債権者に対して受任通知(債権調査票)を発送します。債権者から開示された資料等を元に正確な債務額を算定します。
方針決定
債権調査の結果、どのような方法で債務整理を行うかの方針を決定します。
債務整理の種類
債務整理の種類は、主に次に挙げる3つの方法があります。
・任意整理
債務者と債権者とで間で支払方法・期間を定めた債務弁済契約を締結する方法です。
裁判所の関与がなく、債務者と債権者とで任意に借金を整理するので、この方法を「任意整理」といいます。
・自己破産
月々の収入の範囲内で返済することが難しく、自宅や土地などの自分の資産を売却しても返済が不可能なほど多額の債務を負ってしまった場合、「破産」状態にあるということになります。その場合は裁判所に「破産手続き」を申し立てることになります。
破産手続きにおいては、自宅や土地などの不動産は換価(売却)して債権者に配当することになります。
換価する財産がない場合で特別な事情がない場合は、比較的早く借金の免責が認められることになります。
ただし、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合、免責が認められない場合もあります。
・小規模個人民事再生
民事再生手続きは、裁判所に申し立てることによって、裁判所の監督の下債権の一部をカットしてもらう手続きで、経営困難になった会社等が用いる手続きですが、「小規模個人再生」という、個人向けの手続きもあります。
この手続きを利用すれば、債務の大幅なカットが可能になります。 また、前述のように、自己破産手続きでは自宅は手放さざるを得ません。
小規模民事再生手続きでは「住宅ローンの特則」を利用することで、住宅ローンを従来通り支払い続けながら自宅を保有することができる場合があります。
過払金請求
債権(債務)調査の結果、お金を払い過ぎていることが判明することがあります。
その場合は、相手方に対して、過払金の返還を請求できます。
くわしくは、当事務所にご相談ください。
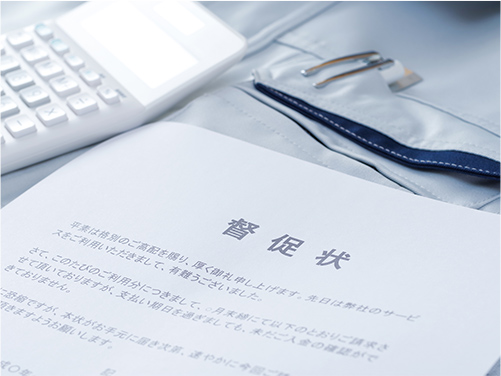
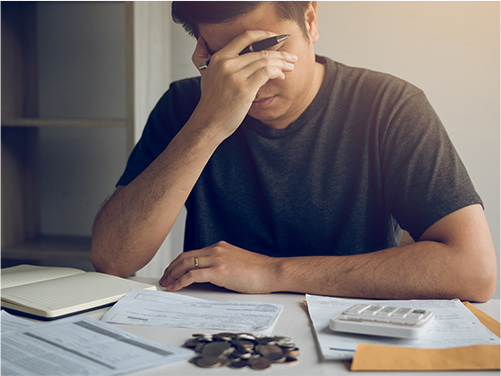

会社・法人関係手続

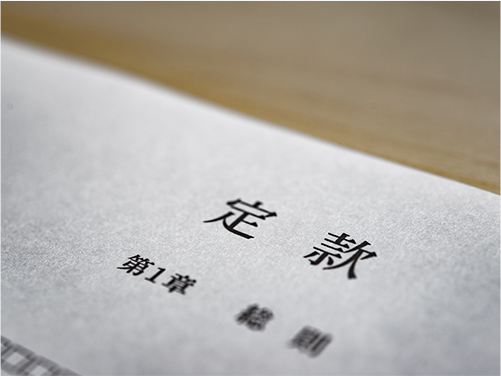

会社の設立 会社を設立する場合、手続きは概ね次の順序で進めていきます。
定款の作成 → 定款の認証 → 資本金の払込 → 設立登記
会社の商号(名称)にどんな文字を使用できるか、取締役(役員)の数・任期はどうするか、設立時の資本金はいくらにするかなど、設立時の決定事項は多岐に渡ります。
当事務所では、会社の設立手続きがスムーズに行えるよう、お客様をサポートいたします。
税理士・社会保険労務士との提携により、税務面・社会保険関係でのご相談にも対応いたします。
定款の見直し
平成18年の新会社法施行により、定款自治という考え方が広がりました。
例えば役員の任期は2年までと法定されていたものが、定款を変更することにより10年まで伸長することができるようになりました。
他にも「取締役会」を廃止することにより、取締役の人数を2名以下にすることができるようになるなど、定款作成における「選択肢」が大幅に増えました。
当事務所では多岐にわたる定款変更事項の一つ一つについて丁寧に対応いたします。・登記を怠ると過料が発生します.。
会社の登記事項は、変更があったときから2週間以内に登記をすることが義務付けられています。
登記を怠ったときは、「100万円以下の過料に処する。」と会社法には定められています。
登記を忘れやすいものに、役員の住所があります。
住所が登記された役員の方が住所を移転されたときも変更の登記を申請しなければなりませんのでご注意ください。
事業承継
昨今問題になっているのが、事業承継の問題です。
創業者が高齢になっても後継者が育成できておらず、事業の継続ができなくなる、というケースは数多くあります。
また、創業者の死亡後、遺産分割協議がまとまらないため会社の株式についても相続する人が決まらず、株主総会が開けない、などということもあり得ます。
当事務所では、事業の円滑な承継のため、上手な遺言の活用法、種類株式の設計、事業譲渡のマッチングなどのご相談についても対応いたします。
